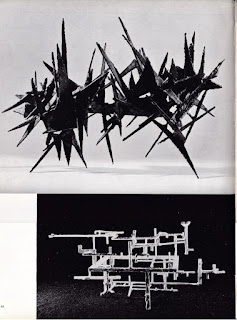『小原流挿花』1961(昭和36)年 6月号から 図7の右端に見える切り株が「L」を表す (次ページの右上のイラスト) *高田一郎氏は舞台美術家、武蔵野美術大学で教授を務められた。 *ペリーコモ・ショーの図以外の舞台美術、装置の制作は、小原流の「いけばなデザイナー」工藤和彦氏とル・オブジェ・アール・スタジオの栗田明氏が関わったとある。 *工藤和彦氏は大正15年、小原流の工藤光洲・光園の次男として東京に生まれた。長男はいけばな評論家であり花道史家であり実作家でもあった工藤昌伸氏。2016年に逝去された。90歳。 https://www.kenbi.info/introduction/profile-kazuhiko/ プロフィール https://www.kenbi.info/introduction/kenbi-3rd/ *株式会社ル・オブジェ・アール・スタジオ(STUDIO L'OBJET ART CO.,LTD.)は、テレビ番組の美術製作・大道具および背景セット・オブジェを行う制作プロダクション。日本テレビ系を中心に仕事をされているという。 https://studio-objet.wixsite.com/objet ************************* 『小原流挿花』1961(昭和36)年 6月号から 陽のあたる場所の背後で ――若々しいテレビの装置―― 高田一郎 「あなたは最近土をふんだことがありますか」――と都会生活をしている人にきいてごらんなさい。 「土ですって?」 大ていの人はまずそういってから、一寸考えるでしょう。 「さあ、そういわれると……そうだ、先月ハイキングにいったときにはたしかに土の上を歩いたけど…」というようなことになってしまいます。 都会に住む人々にとっては、自然は遠のいてしまい、たとえ小さくとも、庭を持って草花を楽しむことなども難しくなってしまいました。 鉄筋のアパートに住み、コンクリートとガラスの壁の中で、人工光に照らされながら働く、現代の私たちの生活様式は昔とは完全に変わってしまいました。 私たちの周囲には、自然の草木のかわりにビルがそびえたち、その間を沢山の自動車や電車がいそかしげに走り廻っています。 このようなメカニックな世界のなかで過ごす、現代の人間の生活感情には、昔のようにのどかな、ロマ...