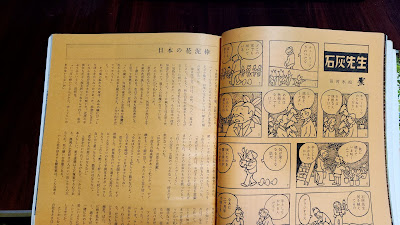1970年4月号《座談会》フラワーデザインの心 出席者 マミ川崎、笠置八千代先生(評論家)、山家直之助(花茂フラワーデザインスクール主宰)、宮嶋敏安(日比谷花壇取締役)、司会田辺徹(本誌編集部) ●独創性ということ 田辺(司会) 「フラワーデザインの心」という抽象的な題になったんですが、この座談会は4月号になりますので、新しい生徒さんもおはいりになりますし、フラワーデザインが日本に広がるようになりまして、すでに、何年か経過したわけですが、ブームのように広がって、それぞれのところに、いろいろな問題もたくさんあるように思いますので、テーマのひとつは、現在第一線で活躍されている方、特に、マミ先生や山家先生などがそうですが、パイオニアの方の問題点、お考え。2点はフラワーデザインを職業としてやっていこうという方もずいぶん出ておりますので、その方たちがいろいろかかえておられる問題がおありだと思います。それから、同じプロと申しましても生徒さんを教えておられるお花の先生、そういう方たちも、きっといろいろご苦労や問題があるでしょうし、これからフラワーデザインを学んだり学ぼうとしている新しい若い方たちが、未知の問題としてこれをいろいろ考えておられるんじゃないか…。 笠置 デザインということばが日本へ来たのは新しいでしょう。昔は生け花というものは師匠から同じものを継承していくという、まねをさせるということで、あれは芸術家ということはいえないわけね、お師匠さんは。そこのところをフラワーデザインというからには今までの生け花とは違うというところをはっきりさせて、マミさんから、どういうのがフラワーデザインかというのを…。 マミ デザインと芸術というものがどういう違いかということも…。 笠置 デザインと芸術は違わないんじゃない?芸術家がデザインするのであって。 マミ でも、いわゆるデザナーというニュアンスは、芸術家というニュアンスとは違うでしょう。 笠置 日本では外来語が変なふうにはいってね。洋服を例にとれば、デザイナーという意味ではほんとうのデザイナーは日本には少ないわね、仕立屋さんに毛が生えたようなもので。 マミ フラワーデザイナーというものも、まだ時期的にはほんとうに育っていないし、私自身もフラワーデザイナーだとはほんとうに思っていないんです。いいデザイナーになろうという努力を毎日続けて