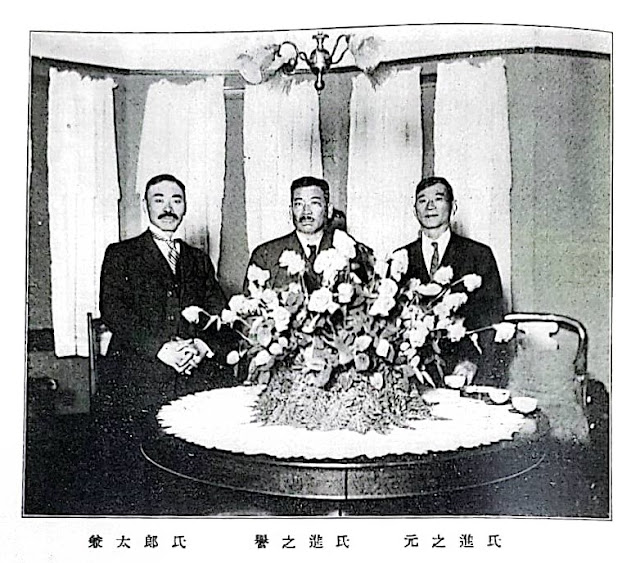いけばなと能楽の関連について
東京教育大学教授、西山松之助氏は、『花 美への行動と日本文化』1969において、次のように述べている。
いけばなが成立した室町時代がどのような時代であったかをみようとするとき、「いけばなだけを見ていくと、かえっていけばなの本質やその成り立ちを必ずしも正確につかめないかもしれない」ので、もう少し広い視点からながめることで、別の共通点を持つ文化現象として明らかになってくるものがあるように思う。
そこで、注目したのは、「阿弥」の号をもつ同朋衆たちの活動である。彼らの出自はいろいろであるが、それぞれが文化活動をするための身分上昇の手続きを経た資格で、「将軍や大名と席を同じくして花をいけたり、能を舞ったり、中国伝来の名器・名画の鑑定や鑑賞を指導したり、ときには金閣・銀閣などの庭園を造営したりする実働の技術者たちであった」。
このような西山松之助氏の指摘のように、室町期の同朋衆たちに共通する場や思想にそって互いに関係し合いながら成長、発展してきたようすについて、大井ミノブ氏は『いけばな辞典』に【いけばなと●●】という項目を立てて解説をしている。
いけばなと連歌
https://ainomono.blogspot.com/2022/03/1976.html
いけばなと掛物
https://ainomono.blogspot.com/2022/03/blog-post_5.html
いけばなと庭園
https://ainomono.blogspot.com/2022/03/blog-post_1.html
ここでは、いけばなと能楽について書かれた部分を抄録する。
*************************
大井ミノブ編著『いけばな辞典』東京堂出版1976
【いけばなと能楽】
中世の芸能は相互に関連し、影響しながら発展したが、それはいけばなと能楽についても指摘されれる。
能の大成者である世阿弥(一三六三~一四四三)が、「衆人愛敬をもて、一座建立の寿福とせり」(「風姿花伝」)と、衆人愛敬*(しゅうにんあいぎょう)を能の発展の根本とした。
これはまた、いけばなにおいても強調されたところで、「仙伝抄」の「三具足に定る花の枝」の条で、三具足の花を序の花とし、「これ花の根本なり。右長は諸神、左短は諸仏、左右に衆人愛敬」と神仏への奉納と同時に衆人愛敬の心持ちを表現している。
いけばなと、能楽とが貴賤上下を問わず大衆に愛される芸能として共通した母胎をもちながら、成長発展したことを物語っている。
それに関して「仙伝抄」に、しんにそえ草をするときの心得を説いて、「たとえば猿楽の笛を吹き、鼓をうちはやして、そのしんを、おもしろく見する様に、花も立つべきなり。」と、猿楽の能で、主役のしてを引きたてて笛や鼓の役割を例に引いている。
また、同書に、元服の花、出陣の花、わたまし*の花、むことりの花、五節句の花など、生活習俗に関する花についてのべているが、能の伝書、「八帖花伝書」にも、婿取・嫁取の謡、門出の謡、移徙*の謡、五節句の謡などとみえて、同様に、生活感情を大事にした共通した関連がうかがわれる。(*移徙:イシ、わたまし:貴人が移転することの尊敬語)
また、同書に、「能と云事、大夫を花の真にたとへ、役者を下草にかたどる。」とのべ、さらに、「囃子と申すは、大夫を本とせり、大夫は一座の大将、花を掌る真なれば、(中略)惣別、役者は大・中・小、大鼓、笛、地謡、狂言に至るまで、花の下草と心得べし。下草は、花の真の賑ひ、威勢あるやうにとばかり心掛くべし。其心得肝要なり。いかに真の振舞は、面白候とも、下草の取合ひ悪しければ、いかにもとしてよき花とは申かたし。」と、真の下草とのとり合わせの大切なことを、大夫と役者との例をあげて懇切に説いている。
このことを、いけばなの立場から、「たとえば、猿楽の能をするに、笛、鼓、太鼓をもって、大夫一人を、おもしろふ見する様に、はやすといへど、つづみは鞍、笛はふへ、一ぶん/\の面白所をなすがごとく、立花六の枝も、能心を生立て、おのれ/\が働有べし。」(「立花秘伝抄」)と、能の例を引いて、心(しん)を引きたる役割として、六つの枝の一つ一つのはたらきの重要さを強調している。
世阿弥が、花をもって展開した能の理論からもさらに、世阿弥が、「風姿花伝」で、「秘すれば花、秘せねば花なるべからず。」「時分の花」「まことの花」などと花の概念によって能の理論を展開したり、あるいは能舞台の背景として鏡板に描かれた松に、能の手向けられる神の影向(*ようごう)する松をかたどったところにも、まさに「花が能に近く候」(「禅鳳雑談」)といった実感がある。《大井》
*************************
*衆人愛敬 (しゅうにんあいぎょう)
能楽の大成者、世阿弥は「風姿花伝」のなかで「衆人愛敬をもて、一座建立の寿福とせり」と述べて上下貴賤を問わず、一般の人々に愛好され、感動されるような芸をもって、能楽の眼目とした。これが中世芸能を貫く根本的な精神である(以下略) 『いけばな辞典』大井1976
いけばなにもこの精神が重視され(「仙伝抄」)、いけばなを通じてお互いが相通じ合う心持ちが重視され、徳とされた。