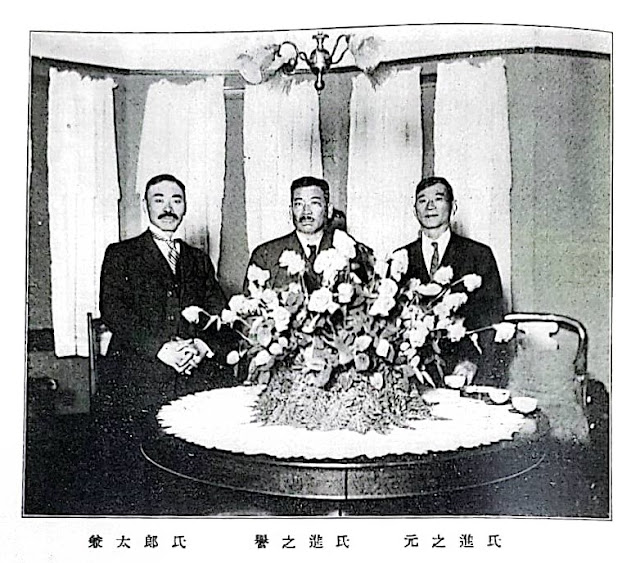若林省三氏、昭和15年結婚して鈴木姓となったバラのレジェンド、鈴木省三氏は応召して海軍の衛生兵として乗船、あまりにも悲惨な現場を経験してPTSDで戦線を離脱するほかなかった。戦争末期、目黒雅叙園は傷病兵の療養施設になっていた。
(昭和15年に結婚し、省三氏は若林姓から鈴木姓となる)こうして結ばれた二人も甘い新婚の夢を追う余裕はなかった。その当時からくすぶっていた支那との関係は悪化の一途をたどり、昭和十六年遂に大東亜戦争という形となって火を噴いた。従ってすべての農業人は食糧増産の責任を負わされ、たとえそれが少い面積の花作りを業とする園芸家と雖も、これに協力しなけれぱならないのであった。併し、とどろきばら園ではこの要請を無視して、ばらを作り続けた。これには明確な根拠があり、信念があったのである。「戦争になれば当然、人心は動揺し、精神的荒廃に陥り易い。こんな時にこそ「花」のもつ意義は深く、その美しさ、優しさが心の慰めとなることは疑う余地はなく、たとえ二、三本の切花、一株のばらを植えることによって、新たな希望と勇気を与えられる」という事であった。
この信念に基いて、ばらを捨てず守り続けて来たのであるが、その反面、色々な苦労も伴ったわけで、供出用の麦を高い価格で近所の農家から買ったり、食糧生産の手段としてばらの株間にジャガイモや野菜を植えたりした。勿論、ばらを買う人などはなく生計は苦しかった。そこで得意であった語学を生かして府立第五中学の英語の臨時講師となり、いくばくかの金を得て生活を守った。殊に幸いしたのは軍需工場に植えるばらの注文があり、当時士官学校の主計官となっていた賛花園の熱田氏のお世話で、そこの庭に植えるばらを納入することになった。この外、大東亜共栄圏会議が帝国ホテルで開かれた際、会場に飾るばらの大鉢を依頼され、予期しない収入を得たことなど。忘れられない思い出であると述懐されている。
こうした軍部と民間人との間に矛盾した行為が当然のように行われていたのであったが、花は知らず、只美しく咲き誇って見る人々を楽しませていた事は確かであり稍々(やや)もすれば荒み勝ちであった将兵の心を柔らげた事も事実であろう。
昭和十九年。遂に鈴木氏の所にも召集令状が届き、横須賀海兵団所属の二等衛生兵として入団、海軍病院で軍医の助手として働くこととなった。その頃は既に第二次世界大戦にまで戦争は拡大されており、戦況は日本にとって不利の状態に陥っていた。多くの傷病兵は病院に満ち、こうした場面に不慣れな鈴木氏にとっては堪えられない苦しみであったようである。病院での勤務の外、瀬戸内海で哨戒船に従って、僅か四、五トンの鰹船に乗り敵機の襲撃を受けて負傷した兵士の看護に当たった事もある。その折受けた衝撃は大きく戦争の悲惨さを身に沁みて感じ、今、思い出しても寒気を催うすると語られている。
こうした精神的、肉体的な過労と栄養不足から遂に勤務不能となり、戸塚海軍病院に入院することとなってしまった。更に八月末、目黒の雅叙園に設けられた臨時療養所に移され、ここに七ヶ月間程、療養生活を送ったのである。ここでは実家も近く家族との語合い、親友知己などとの接触も出来、精神的な慰めを得ることが出来たことは幸せであったと思う。
昭和二十年春頃、漸く退院されたのであったが、退院後は暫く休養を必要とし、その間にばら園の復興計画を検討し、やがて訪れる平和時代に備えた。幸い鈴木氏の所では、ばらを保存しておいたので、ばら園としての立直りは早かった。
※船上で爆撃を受けて負傷するということはこのような状況になります。(現代農業のサイトから 農家の戦争体験記)