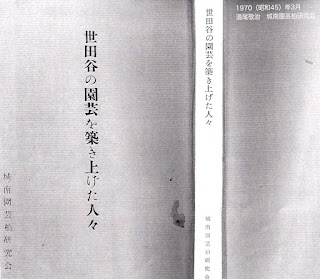玉川温室村を支えた人々(5) 加藤昇之助氏、植松清農園 『世田谷の園芸を築き上げた人々』1970から
『世田谷の園芸を築き上げた人々』 湯尾敬治 城南園芸柏研究会 1970
※一部の漢字や送り仮名等を読みやすく直してあります。
温室鉢物栽培の 加藤昇之助氏
温室村の加藤氏は、大正十一年に園芸学校(※東京府立園芸学校)を卒業されている。造園家の吉村厳氏、元玉川仲町に貸鉢業を営んでいた篠田氏などが同級生であったそうである。
園芸学校卒業後、千葉高等園芸学校に入学、大正十四年卒業、直ちに戸越農園に実地研修のため入園された。ここでは主として温室ブドーの栽培を研究し、将来、この方面の経営を目的とされていた。昭和二年、現地に温室百坪を建て、ブドー栽培をする予定であったが、よく調査して見ると地下水が非常に高く、とてもブドーには適さないことが分り、これをあきらめ、カーネーション、メロン、トマトなど栽培することにしたのであった。
昭和八年頃、更に二百坪増設して、カーネーション二百坪、球根類(百合、チューリップ、水仙)、カランセ(洋種のエビネ蘭)などを栽培されたのであった。加薩氏のメロンは高級園芸市場でも評判よく、常に百匁三円位の高値で取引きされ、一個九円(三百匁位のもの)にもなり、一箱に十二、三個入れて肩にかついで行っても百円以上になったので、出荷のための肩の傷みも忘れる程、楽しかったと述懐されていた。トマトも百坪の温室で栽培、神田市場や、新橋の和泉屋に出荷していたのであるエビネ蘭も二十坪位の栽培面積であったが、一本二円に売れたのであるから、当時としては高級品扱いされたようであった。
氏のご子息も園芸学校の卒業生であり、千葉大学造園科を卒業後、地方の各県庁に勤務、公園の設計施行の指導をされ、現在は島根県庁に在職されているそうである。
昭和十九年頃は第二次大戦のため。石炭の入手も困難となり、召集による労力不足に加え、空襲による危険も伴い、温室の取りこわしも止むなきに至ったのであった。物資は極端に不足し、衣食住は勿論、軍需工場用資材も不足していたため、古ガラス、古鉄など、温室建築当時の二倍以上に売れた。ガラス一枚五円に売れたのであるから、予期しない収入源となったわけであったが、生活を支えて来た温室がなくなったことは、悲しい限りであったのである。古材木は燃料とし、とに角生き抜くためには、何もかも犠牲にしたわけであった。
戦後は、小じんまりとした小温室で、シクラメン、ゼラニューム、君子蘭、ベゴニヤなどの鉢物を栽培した。シクラメンの高冷地委託を試み、昨年、間島、辻氏らと西多摩郡桧原村に預けたが、氏のものは病菌発生し思うよりな結果は得られなかった。委託に出す前、充分の予防策を講じておくことが大切であることを痛感されたと云う。
シクラメンの委託について一つの意見をもっておられた。それは現在のように四、五寸鉢に仕立ててからの委託は、運送に時間と労力を多く必要とするので、これを小苗の時(三、五寸)運び現地で鉢上げするようにすればよいのではないか。勿論、委託日数は長くなるわけであるが、結果的には得策と云えるのではなかろうかと。更に三寸鉢位の時委託地の農家に買い取って貰らい、自分のものとして栽培管理する方が、欲と愛情によって研究心も湧き、よい成績を挙げることが出来るのではないかとも云われる。但し、この場合、徹底的に技術の指導を行う必要がある。十月に入って引取る際に、委託料の中から苗代を差引く方法も考えられるとのお話しであった。
何はともあれ、委託栽培には両者一体となっての管理が絶対必要であり、徒らに利害関係について云々し合うことは避けねばならんと思う。お正月に第一園芸の石田さんを訪ね、シクラメンの話しをした所「自分で作ってさえ、気に入るように生育しないのに人に任かせておいて、よく出来なくても文句は云えないだろう」と云われたそうである。
土地価の非常に高い都市で、生産性の低い草花栽培に、長い時間をかけていたのでは到底引合うものではない。半成品を購入し、二、三ヶ月で成品化して換金するような態勢に変って行くべきではなかろうか」とのお話もなされた。加藤氏は明治三十五年の生れであるから既に六十七才位になっておられるわけであるが、中々の元気で朝顔の苗を丹念に作っておられた。温厚そのものの氏の性格は、セチ辛い現代に背を向けて、至極のんびりとして花作りを楽しんでおられる姿に、一種のうらやましさを覚えたのであった。
住所 大田区田園調布四の四の四二の四
カーネーションの植松清農園
植松氏は静岡県沼津の人、昭和五年、二十二才の時、温室村の長門氏の所に研究生として入り、四ヶ年の修業を経て、昭和九年に独立経営に移られたのであった。その最初は、早川源蔵氏の温室を譲り受けたもので、暖房なしで、菊の栽培をされていた。坪数は五十坪、大輪中輪を組合せ、セードカルチから晩生種の「東の光」「東光の調べ」などの品種も交えて、厳冬を除き、出荷のとぎれのないように工夫した経営法をとっていたのである。温室の外、露地でも、小輪中輪、各種の品種を栽培し、カーネーションの露地栽培も行い「園芸」という仕事のむずかしさと、楽しさを体験されたのであった。当時の品種は、洋菊系には、オリフラム、ターナー、シトロニヤ、サングローなどがあり、和菊系としては新東亜、前記の東光の調べ、東の光など(伊藤東一氏作出の菊)であった。
昭和十九年、第二次大戦のため、名古屋第三師団へ、衛生兵として召集され、三ヶ月間の勤務で除隊したのであったが、戦局は既に悪化の一途をたどっていた。「園芸」という仕事もぜい沢品を作る職業として、中止の止むなきに至り、温室は売却し、一時埼玉県の親類の所に疎開していたのである。昭和二十四年に上京。現在の地で、野菜苗、自家用野菜など栽培する傍ら、露地草花も作って収入の道を計っていた。世情も漸く券付き、切花の売れ行きも上昇して来たので、昭和二十七年に六十坪の温室をたて、次いで六十坪を増設して、百二十坪とし、暖房設備を整えて本格的なカーネーション栽培をはじめたのであった。露地カーネーションも取り入れ、周年出荷の態勢で、切花の好況時代に対処した。この頃は、カーネーションのみならず、一般切花の最も高値を示した時代であり、カーネーション一本二十円位、暮には五十円、六十円の高値を示し、洋、和菊共一本七、八十円に売れたのである。
植松氏は専ら、中輪のピーターフィシヤ系にコーラルであり、量より品質に重点をおき、一坪六十株、一株より十二本の切花を得ることを標準としていた。最も収益の挙った年は、坪一万円であったが、昭和三十年以後は漸次、下降楾をたどって来た。このことはこれまで幾度となく述べて来た通り、戦後、地方園芸が急激に発展して来たためであり、到底避けられない時流であったと思われる。
この頃から、カーネーション栽培家は、大輪種に注目しはじめた。その初期には非常に人気があり、漸次、ウィリアムシム系に替えて来たのであった。植松氏は、こうした傾向に目をくれず、ひたすら、中輪種で優秀なものの生産に全精力を集中し、花持ちのよい、大輪種に迫る大きな花を咲かせることに努力した、年毎に中輪カーネションが少なくなって来た中にあって、植松氏のものは市場でも人気があり、年間の収入は大輪種栽培家に劣らない程であった。
併し地方のカーネーション栽培は異常なまでに栽培技術が進歩し、荷造りの改善や、輸送機関の発達によって、東京産のものに劣らない良品が生産されるようになった。従って温室村のカーネーションの市価も横ばい状態を続け、一般物価の高騰に比して必ずしも調和するものではなかった。
この頃から鉢物の需要が高まり、温室でも露地でも、一般草花の鉢作りが盛んになって来た。植松氏もここで小菊の玉作りをはじめ、懸崖作りも多少取入れ、カーネーションの収入減をカバーすることに努めた。もともと研究熱心な氏は、誰よりもよいものを作ろうと菊作りの先輩諸氏の所に足を運び、色々と指導を受けた。氏も後継者はなく、(ご子息は法律を学び他に就職)只、一人で頑張り、わずかに、アルバイト学生を頼む位であったが、玉作り、五千鉢、懸崖菊二百鉢種栽培し、全部庭先き販売で処分し、持ち前の負けず嫌いを遺憾なく発揮したのであった。
これ程、花作りに意欲を燃やした氏が、突如として温室を取こわし、アパートを建てた。私は唖然として、その真意を疑った。まだまだ働ける年令であったし、土地は自分のものであった、とは云うものの主作のカーネーションの将来には希望はもてなかったし、玉作り栽培も骨が折れて来たようであった。六十才近くなれば、誰しも、これからの人生について考え直して見る事であろう。ぢり貧の園芸経営を続けることは決して得策ではない、と考えられたようである。努力家であった反面、見切りも早かったようで、私がお尋した時のお話しにも、こうした考え方が多分に含まれていたのであった。併し花に寄せる愛情は消え去る筈はなく今後も、菊作りを続け最後まで花と共に生きることを希っているときいて、私もほっとしたのである。
住所 世田谷区玉堤一の一四の一三
電話 七〇二‐二○九七