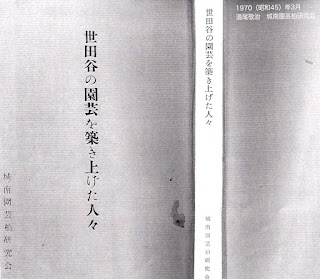玉川温室村を支えた人々(6) 荒木石次郎氏、秋元農園、ほかに小杉直氏について 『世田谷の園芸を築き上げた人々』1970から
『世田谷の園芸を築き上げた人々』 湯尾敬治 城南園芸柏研究会 1970
※一部の漢字や送り仮名等を読みやすく直してあります。
スイトピーの 荒木石次郎氏
昭和の日本園芸史を飾る第一頁は、何といっても温室村の花卉園芸であったろう。ここに最初の足跡を止めたのが荒木石次郎氏であった。大東亜戦争の初期で八百五十坪の温室を有し、スイトピー、カーネーション、ばら、メロンなどを栽培しておられたのである。
氏は北海道の生れであり、小学校卒業後、土地の建設会社に勤務された。ここで田中銀次郎氏の知遇を得、氏の身辺に関することはすべて田中氏の配慮に基いており、親とも師とも仰ぐ恩人であった(※田中銀次郎氏は北海道で明治から昭和にかけて活躍した建設業の重要人物)。二十才の時、園芸を志し東京府立園芸学校に入学する決心をして上京した。氏は農家の出身であり、小学校のみしか卒業しておらず、園芸学校の入学資格はもっていないのであったが、当時の山本正英校長に「何とか入学させてほしい」と懇願した。氏は英語を不得意として全然分らず、入学試験を受けるにしても自信などあろう筈もなかったが、とに角試験を受けることにした。幸い合格者の中に自分の名前も加っていたので、山本校長の理解ある処置に感謝したそうである。
入学したからには誰にも負けてはならんと苦手の英語はもとより、専門教科など人一倍勉強した。その甲斐あって昭和十一年、無事卒業(第十三期)当事沼袋にあった。中野定作氏の農園に研究生として入園された。中野氏は農業大学出身であり、ばら、カーネーション栽培を主とし、約一千坪余の温室をもっていたそうである。ここで一ヶ年間勉強し、目黒の菜花園にも僅かの期間であったが、研究のため働いていたことがあった。
その頃、荒木氏を全面的に支援されていた田中氏は「どうだ、アメリカへ行って園芸の実際を勉強して来ないか」とすすめられたのであった。併し、荒木氏は「同じ花を作るなら、アメリカへ行かなくとも、その分だけ日本にいて栽培した方が、早く実力がつく」という信念から、そのことを断り、早速、独立経営の計画を立てた。
当時、田園調布(温室村)は区画整理が済んだ許りで、田圃は多摩川を改修した残土で埋めてあったが、道路には砂利を敷いてなく雨が降ると、ドロドロの悪路となる有様であった。ここの地主は落合孝之助氏であり、信用組合長でもあったが、花を作るために、二千余坪の土地を借りるということに一種の不安感を抱かれていたそうである。併し荒木氏を絶対信用している、先きに述べた田中銀次郎氏が保証人となるのであったから、賃貸契約は無事に済まされたのであった。この契約書の内容をそのまま、あとから入居した園芸家の皆さんにも適用されたのだそうである。
そこで早速百坪の温室を建てて、カーネション五十坪、ばら五十坪植付けたのであった。これは氏の弱冠二十三才の時であり、大正十二年十二月であった。氏は短い期間の実際経験から独立経営に移られたので、色々な面で苦心されたようである。スイトピーの栽培などあまり予備知識はなく、外国のカタログ(アメリカ)に記載されていた栽培説明など参考にしたと云われる、不得意の英語であったが、園芸学校卒業以来、色々な機会を捉えては英語を勉強したおかげで、外国のカタログや園芸書など判読出来るようになったそうである。こうした努力が報いられて、他の人よりは一歩先んじて、スイトピー栽培の要点を掴んだ様子であった。この後作にはメロンを取入れたのであったが、当時、三軒茶屋でメロン栽培をしていた五島氏や先輩の榎本一郎氏などの栽培法を参考にして研究したそうである。
こうして荒木氏は着々と事業の拡大に意欲を燃やし、百坪からスタートして、一年おき位に百五十坪位の温室を増設して行った。これに要する資金は必ずしも園芸業による収入というわけにはゆかず、落合氏の協力を得たことも度々であったと云う。併し、その借金は必ず返済してきたので、経営の面では順調に伸びて来たわけであった。
この辺で氏の専売特許とも云うべきスイトピー栽培の秘訣?について述べて見たいと思う。この花は豆科植物であり、徒長するようでは花着きもわるく、落花し易い、そこでベッドの下には廃物となった瓦を敷き、その上に植土を盛った、石灰を混じて酸性の中和を図り、魚肥、未糖、過石など混入して二、三ヶ月放任しておく、定植は九月上旬であるから、それまでに醗酵腐熟するので、スイトピーの発育には支障はないという。種子は直接輸入であり、それを選別して布に包み、井戸につるしておく。約三週間こうしておくと、程よく湿気を含んでふくらんで来ており、低温の刺激も受けているので発芽揃いもよいのであった。これを八月下旬小鉢に蒔き、フレーム内のよしず下で管理し九月上旬定植する。スイトピーの採花適期は、頂点の花まで開花したものでなければならない、切ってからでは蕾は開花しないという。採花の方法も一般的には鋏で切りとるのであるが、荒木氏は花梗の付根からもぎ取るのであり、その方が水錫げがよく、従って花もちもよいと云われる。特に変っている点は荷栫らえしても水につけない事である。このことは水揚げしてあると出荷の途中、もまれて花傷みを起し易いからであった。多少しおれていても、花屋の手に渡ってから水揚げすれば、品質には少しも変りはないのであった。こうした、栽培から出荷まで工夫したスイトピーは、常に他のものより二、三割、高く取引きされていた所以であった。
カーネーションなどは、あまり出来のよくないことが度々あったが、或る時、特に不出来の一ベンチを早い時期に引抜き、普通のものより一ヶ月以上も早く定植した所、それが非常によく出来て坪当りの収入では他のものより二、三倍も多かった、とのお話しであった。栽培種類の各々の坪当収入をおききした所、「私はあまりこまかい計算はしない主義である。計算事に費す時間を栽培や荷栫らえに当てる」との事であり、尚、その時、その折りの作柄や、市価に支配されるので、一概に何千円の収入になるかということは、言明出来ないとも言われたのであった。
メロンなども現在、静岡などで行われているような栽培法では味のよいものが出来る筈はない。地ベットであり、たとえ敷わらをしたとしても毛細管の作用で、必要以上の水分を吸収してしまう。どうしてもべンチ作りとし、水と肥料の加減調節し、充分の日数(五十五日)をおいたものでなければ、マスクメロンとして価値のあるものは生産されない。たとえ、ネットはきれいに現われていたにしても、水分が多うかったり、早取りしたのでは露地作りのメロン類に等しい、と批判される。
切花の最盛期には、カーネーションー千本、ばら千本、スイトピー三千本位あったので、夜中まで花束ねにかかるそうである。園丁さんも七、八人おり、一人百坪が栽培管理に適当な坪数とされており、氏の所でも多い時は十人位も見習生や雇人が居たのであるが、中々忙しい毎日であったと述懐されている。
こうして、八百余坪の温室栽培に情熱を燃やしていた荒木氏も、昭和十八年には戦時体制の下で、国策に協力するという意志もあって、全部の温室を昭和電工KKの傍系会社であった朝鮮電工KKに売却してしまった。その価格は忘れてしまったが、十三万円か十八万円位であったろう、とのことであった。氏は昭和十六年頃、日本橋に荒木産業KKを創設しておられ(事業内容はおききしなかった)園芸業をやめられてから、その方の仕事に専心されたようである。察するに荒木氏は常に進歩的に行動し、企業に関しての経営手腕も持ち合わせておられたようである。私は卒直に、「各々の企業に関する專門的知識がなくとも、その経営に支障はないものですか」とお聞きした所「要は人材を集める熱意と、それを有効に利用する配慮が必要なのである」と答えられた。
私のお尋ねした場所は、多摩川のほとりであり、第三京浜国道の下であった、清水電気KKといい、電気関係の仕事を請負って施工する会社であり、事情があってこの会社を経営することになったのであるが、前者の名称をそのまま利用しているのだ、と説明された。
氏も私の計算では七十才の老人仲間と思われるのであったが、ガッチリとした風格には少しの衰えを見せず、中々の元気さであった。私は「世田谷から次第に花作りが減って来て淋しく思っている」と話した所「今となっては花作りでは発展しない。花作りは地方に任せ、我々は常に時代の要求する仕事を発見して、それに対し自己のもつ力の限界を試して見ることだ」と語っておられた。
氏は過去の世田谷の園芸家の中では異才に属するものであろうが、性格的にも進取の気性に富んでおり、時代の変化に応じてより有意義に生き抜こう、とする意欲が、今日の荒木氏の姿であろうと思うものである。
住所 大田区田園調布七の五三の四
電話 七二一‐三二四五
貸鉢の 秋元農園
温室村の秋元藤夫氏は、かつて三百余坪の温室をもち、カーネーション専門の園芸を経営しておられたのであった。昭和三十年頃から起った、切花園芸の変移と、一方には貸鉢業の発展性が注目されて来た。氏もカーネーションの将来に不安を感じており、この際、時代の要求する貸鉢業に転向する決心をされたのであった。
秋元氏は、東京中野の生れであり、宮崎氏と同じ町であった。大正四年の出生、本年五十五才の壮年である。旧制日本中学を卒業、園芸を志し、昭和十年二十一才の時宮崎氏の農園に見習生として入園、以来五ヶ年間、氏の薫陶の下で園芸家としての技術を修得されたのであった。
昭和十五年、現在の地に独立、カーネーション専門の園芸をはじめられたのである。ここは元退役海軍大佐、田中氏の経営していたものであり、七百坪程所有していたのであったが、そのうち三百坪を秋元氏がゆずり受けたのであった。当時の金で一万円であったそうである。氏はここで独立の第一歩をふみ出したのであったが、時既に大東亜戦争のはじまる直前であり、花卉園芸そのものの将来に一抹の不安があったのである。併し、そんなことにかかわってはおられず、一ヶ年間は夏切りを主体にして作付けを行った。それでも最盛期には五千本の切花を得た程である。1本五銭位であり一回の切花で、二百五十円の収入を得ることの出来たことは、氏にとって大きな力付けとなったのであった。
こうして独立二年目を迎え、いよいよ本腰を入れてカーネーション栽培に力を入れようと張り切っていた矢先き、昭和十六年の十月、赤紙ならぬ白紙の三ヶ月召集令状なるものが届けられたのであった。氏は徴兵検査の結果は第二乙であったが、この令状により近衛野砲(世田谷)に入隊することになったのである。併し、三月兵であったから翌年一月には除隊することになった。この年十二月八日、遂に日米開戦という最悪の事態に突入し、氏は再び召集を受け、再度、近衛野砲に入隊したのである。今回は新兵の教育助手であり、比較的楽であった。軍馬の運動のための外出時、多摩川べりを通過した折りは、自宅に立寄り友兵と共に休憩したついでに、カーネーションの状態を調べたり、管理の手順などを奥さんや、管理人(留守中は隣りの飯田さんに依頼しておいた)に指示したのである。この時は百坪は解体しており、二百坪だけ作付けしてあった。
昭和十九年六月、召集解除になり一安心したのも束の間、又々二十年の一月召集されたのである。国土防衛隊として茨木県の鹿島地区に派遣され、敵機の襲来や敵前上陸の警備に当ったのであった。幸い身辺に異状のないまま、八月の終戦を迎え九月に帰宅出来たのであった。併し、花ばかり作っているわけにもゆかず、野菜苗を栽培して大田区の馬込地区の家庭に配給した。どこでも花作りをやめていたのであったが、氏は七十坪の温室でヵカーネーションを作り続けたのである。燃料などある筈もないので、夏切りとし、いろいろ工夫して初冬まで切花を得られるよう努めた。花など買う人のないと思われる終戦直後ではあったが、一本五十銭に売れたので大いに気をよくしたのであった。その翌年は五円となり更に十円となった。昭和二十二年頃、一本七十円に売れたこともあった。このことは花が少なかったことは勿論であるが、アメリカ進駐軍の需要があったので、この高値を呼んだのである、二十三年頃は平均三十円位の相場が続き、一坪一万円の収入は普通であったようである。取引きは花屋に直接売るのであり、下谷市場の松本社長自ら荷を取りに来たそうである。
温室の暖房など満足なものは備えられる筈もなく、ストーブを使い煙突を伸ばして、亜炭という軟質炭を燃やしていた。温室の周囲は古シートなどで囲い保温につとめた。ストーブではどうにも厄介なので、マリンボイラーを取りつけて亜炭を燃やし続けたが、昭和二十七年頃、これにバーナーを取りつけて重油に切替えたのである。秋元氏の温室も田中氏時代のものであり、戦中戦後何等手入れをしてなかったのでかなり傷いて来た。思い切って大修理をして、一応、現在の形を整えたのであった。
昭和三十年頃から地方に花卉栽培が盛んになりはじめ、東京の園芸家は打撃を受けるようになってきた。その反面、都市には利用園芸が活気を呈して来たのである。このことに着眼した氏は、友人の花政(中原)と相談して、貸鉢業の共同経営を計画した。資本金三十万円也、材料の栽培は秋元氏の役目であり、お得意の獲得は花政の役目であった。幸い仕事の方は順調な伸びを示したのであったが、材料の方がそれに追付かなかった。幸い八丈島に知人がおり、そこで栽培した観葉植物を代金あと払いで、必要量送って貰った。鉢の方は近江化学から、これもあと払いの約束で仕入れ、とに角需要を満たしたのであった。幸い氏には多少の不動産があり、これを資本の一部に役立たせたそうである。
貸鉢業の対象とたる企業体の主要部門は、既に従前からの業者によって占められており、その間に立って顧客層を拡げて行くには、或程度の無理押しも止むを得なかったようである。
こうして三ヶ年間、共同経営を続けたのであったが、必ずしも利益金として残るものは少かった。その上運悪るく、昭和三十三年の秋、豪雨のため六郷用水が氾濫し、氏の温室も浸水し貸鉢材料に大きな被害を受けたのであった。これを機として花政との共同経営を解消し、新らたに秋元個人の事業として再出発することになったので ある。材料は傷められる。借金は残る、併し強気の氏はこれを乗り越えるためにあらゆる労苦に堪え、所有していた土地も手放して、再建の資本に充てたのであった。
貸鉢業は基本的に、貸出してある数の三倍の材料の保有を必要とした。貸出しの増加に対処するための予備的なもの、傷みの快復のため栽培中のものもあるわけで、これらの置場所もかなりの坪数を必要とするわけである。幸い氏の所は二千余坪の土地をもっているので(借地)、充分とはいえないまでも、約三千鉢の貸鉢をおいてあるそうである。置場の少ない業者は、必要に応じて買入れ、傷んだものはどんどん処分してしまうという。資本回収には略々三年かかり、一年目は植木代(鉢を含む)二年目は燃料其の他の消耗費、三年目は人件費ということになると説明された。但し、これは決定的のものではなく、事業の性質上、もろもろの条件変化によって差異の生ずることは止むを得ないであろう。一鉢の貸出し料も、一応組合の協定価格はあるものの強制されるものではなく、材料、貸す期間などによって差の生ずることは当然であり一律には行かないのである。尚、建物の構造、置き場所、季節などによって材料の選定と期間を考慮しなければならない。例えば、アレカやしは冬の貸出しはしない。ケンチャやしは九月から十一月までの貸出し、シュロ竹などは冬の期間だけ貸し出すという。フェニックスやゴムの木は周年使用に堪えるものであるが、それだけに日頃の栽培管理が大切である。要は材料を傷めないように、常に新鮮々姿で貸出し出来るように心がけることが、貸鉢業者の良心であり、営業策の一つでもあった。
こうしたお話しの外、傷んだ植物の快復方法、労力不足に対処するための農場整備、カーネーション栽培に関連した、信州のカーネーションの産地化、これの気象条件、今後の都市園芸に対する批判など、色々お聞きしたのであったが、今回は省かせて頂くことにして、秋元氏の貸鉢業者としての人生観乃至は園芸観を述べさせて頂くことにしたい。
すべての商売がそうであるように、貸鉢業者としても例外ではなく、お客に対しては頭を下げて礼をつくす。相手は頭を高くして支払者としての偉厳を示そうとする。商売はお客に威張らせておき、自からが頭を下げる代償として利益を得るのだ……と。この点、草花栽培者は美しく咲いた花を眺めてから、市場なり花屋さんに売ることが出来る、それも頭を下げる必要はなく、むしろ威張っていても仕事は成立つ。(今後の経営には多少変化は起るであろうが)、更に貸鉢業者の農場は植木の病院みたにいなものである。疲れ弱っている鉢物を手当てして元の姿に快復させる作業が多い。美しくなった瞬間、外に出してしまわなければならない。こうした苦労の分だけでも、他の園芸家よりは何等かの形で報いられなければならないと思う。そこで多少、一般園芸よりは利益も多いと思うし、そうでなければ利用園芸としての価値もないわけである(但し、これはどこまでも比較論である)。併し、他の大企業と比較しては矢張り零細企業でしかなく、元来、好きではじめた花卉園芸から、それの延長に等しい貸鉢業に転向したのみであり、本質的には植物を相手とする職業で、生物を育てる心情は花卉栽培者と変りないのであった。毎日の労働に比較してその報酬はあまりにも低い、この現実の中で何に希望を求めるか、それは土地保存であり、土地の値上りによる生活の安定感であろうと氏は言われる(この外、園芸人としての植物を育てることの楽しみのあることは勿論である)。貸鉢業の大御所、東光園主もこのことに触れて、「官庁の役人の何倍も働いているのに収入は少ない、恩給もつかない。何と因果な商売だろう。好きではじめた仕事だから放り出す気にもなれない。せめて土地の値上り分を恩給と思えば、あきらめもつく」……と秋元氏に語られた そうである。これが都市近郊で農園芸を営む人の共通した考え方のようである。何はともあれ、他を羨ましがることは毛頭ないのであり、自己の現在の経営に最善をつ くすことに、生甲斐を持つことであろうと私には思えた。
お話しがたまたま花の安いということにふれ「これは日本人の性格が微妙に働いているのではないか、日本人は物を大切にする国民であり、花を眺める場合でも少しでも長く楽しもうとする。一方では風流を貴ぶ民族性ともいうべき心情を抱いており、一本の花が蕾から開いて万開となり、更に散り果てるまで、その間の変化に無上の 楽しみと、哀しさを味うのである。従って一鉢の草花でも蕾のうちから楽しみたいのであった。これでは中々たくさんの花は売れないであろう。欧米では満開の花を大 ざっぱに買い、一日眺めて捨てる場合が多いという。国民所得の低いことも原因であろうが、根本的には貧しかった長い歴史の上に積み重なった民族性であろうと思わ れる。自分も長い間、栽培家として生きて来た関係上、思い切って傷んだものを捨てられないで、何とか生き返らせて見たいと丹精するのであるが、これは企業として妥当であるかどうか疑問である」……このように語っておられる。私としては物を大切にすることは自分の仕事を大切にすることであり、自分自身をも大切にすることに通ずることであり、秋元氏の発言には心から賛意を表すものである。但し、これにも限度があり、人件費昂勝の折、その企業体の性格及び、人員構成の状態など、色々な要素の分析の上に立って、取捨選択することであろうと思われる。
住所 大田区田園調布
番外
都立園芸市場創立者 小杉 直 氏
小杉氏は目黒、柿ノ木坂で農業を営まれていた。畑一町歩位に竹山がたくさんあったそうである。園芸学校卒業後、露地切花や地堀物を栽培しておられたのであったが大東亜戦争が激しくなった頃、徴用工として富士航空計器KKに働くことになった。不幸にして二十年五月の東京空襲の際、住家を焼かれてしまい、止むなく現在の土地を買い求めたのであった。約四百坪であり、一坪千円であったそうである。戦後、ここに八十坪の温室をたててカーネーション栽培をはじめられた。この時の苗は植松清氏から分譲して貰ったそうである。氏はここで、カーネーションを作りながら生花市場設立の構想を練ったのであった。
小杉氏は他人の面倒をよく見る人であり、自分のことは二の次として、これから花作りをはじめようとする人の世話をされた。目黒の辻氏、中島氏、深沢の鏑木氏、私なども色々とお世話になったのであった。川崎の小田中におられる内藤氏や田中氏も、小杉氏の指導で花卉園芸の勉強をされた人であり、遠くは信州の滝沢氏、伊豆や銚子などにも園丁をしていて独立され、それ以後、色々な面でお世話になっている人達もおられるのであった。
市場設立は昭和二十七年であり、年々、出荷量と共に生花商も集り、当地区では只一つの生花市場として、生産者の利用が多うかったのである。特に地掘り物は城南地区唯一の出荷最があり、これを目的として各地区の花屋さんが集った。
都市化の波による地元生産品の減少は避けられなかったが、それに代って、長野、房州、愛知などからの出荷が増加して来た。現主、小杉喜四郎氏は父君の遺業を継ぎ、今日の生花市場経営に努力されているのであった。
ここに出荷される花の中で特質あるものは、長野のカーネーションであるが、これは小杉氏が山廻りの折、常に地区の農家と会合して、カーネーション栽培の技術指導に当っておられたことが要因となっているようである。カーネーションの大手出荷である滝沢氏も、その中の一人であり、小杉氏の苗五万本位栽培されたこともあったと云われる。こうして、営々十年の市場経営の中で、色々と波乱のあったことは何処も同じであり、よくそれを乗り越えて来られた所に、小杉直氏のねばり強さと人徳が秘められていたものと思われる。
昭和三十六年、五十五才をもって他界されたことは、地区園芸家にとっては淋しい限りであり、都立園芸市場が今日の発展を見せたことが、せめてもの慰めであるかも知れない。現在は、二男直久君が主になって、これからの小杉農園を築き上げて行く決心をされているのである。直久君が学校在学中は奥さんが主になってご主人の遺された温室を守って来られたのである。今後は鉢物を取入れて多様化を計りたいと話しておられた。
園芸学校で白ピーターの枝変りとして発見された、「東園の粧」が温室の中で咲いていたのでなつかしかった。白地にうす赤のしぼりの入ったこの花は、市場人気も非常によく、他へは出したくないとの事であった。但し長野の滝沢氏だけは分譲してあるそうである。この品種をもっと殖やして、カーネーション栽培を充実させたいと奥さんは語っておられ、これからも園芸に直久さんと二人で力を入れて行きたい、と語っておられた。