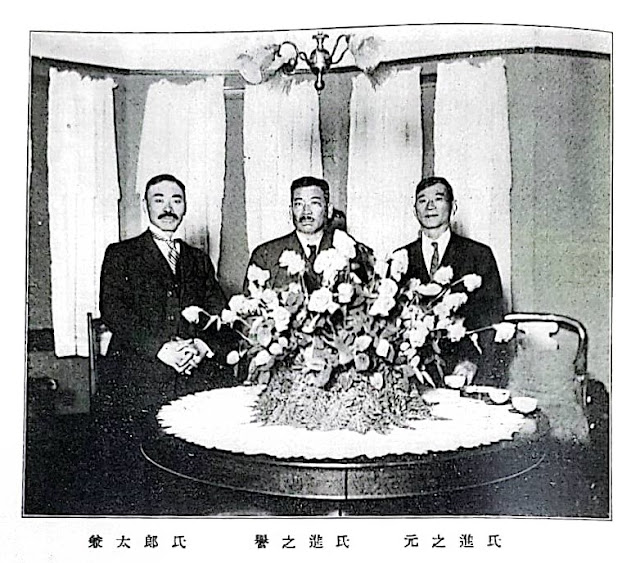豊雲雑感 道行くものの心構え
『花道周辺』小原豊雲 河原書店 1950年
豊雲雑感
今までの花道人は、貴人に近づくのを光栄としていたが、事の実質を離れて、単に光栄をのみ考へるのを自分はよしとしない。如何なる作品を自分がなしたかに何故自負を感じないのであらう。
○
花は時の間に過ぎゆく芸術である。その為に、作品が長く伝はらず、ひろく世の批判を得、後世にその芸を遺すことは難いが、その代り、他の芸道に見られない特質がある。譬へば、絵画であるが、これは、絵具をもってかくだけ、草木を表現するにしても、他の材料によらねばならない。その点になると、花道は、偽らざる自然のものを其儘に用いる。譬へ散る花であつても、生けられてゐる瞬間は、より自然に、より美しい。正確に云へば、自然のものを扱ひ乍ら、これを表現する芸が伴っていなければならないが、それを具へた花であれば、如何なる絵具をもってかゝれた絵より以上である。
これは挿花の特質であると共に、それに満足する日本人の性情がこゝにあったからである。散る桜への趣味が云はれているが、これは、やがて挿花の様な芸を成(*なり)立たせた理由で、この命短かきものの至上なる麗しさをおしむことに、日本人の生命感があった。
○
命短かき自然の草木を用い、散りゆくものに時の間を感ずるのは、実は、それをもってして表現されるぎり/\の何等かの感情があったからである。ここから新しく開かれていった世界は、徒らなる思想であるよりも、天地の中にある真の現実を見つめることであった。この現実から光を与へられることに、慎しい個性とその自然感が導かれる。
○
世間には二つの型がある。譬へば表の宗匠の即中齋と裏の淡々齋宗匠であるが、この二人は色々の意味で興味ある対照である。私はこのお二人が同一の場合に演じた別々の動作を見た。ある百貨店で何かの催しがあり、二人の宗匠に謝礼のしるしを差出した時、裏の宗匠は、イヤ/\そんな事はと云ふ風に手を振って。その場を辞去した。そのあとに、付いてゐる人があって有難くそれを受取っていった。けれども、表の宗匠の即中齋は、先方が包みを差出すと、「それはどうも有難う」と、自ら手を出して素直に懐中におさめた。詰り、それだけの相違があるわけである。
この二つの差は何時の時代にもある。スタイリストと云はれる人々は、世間に対して効果ある構へをよく知っているが、それに構らない他の人もある。茶花道の方ばかりでなく。その他の方面にも、この構へをよくする人は多くぁる。
然し、私はどうもスタイリストにはなれない。この夏も、北海道に旅行したが、私自身がトランクをかついで歩いた。駅につくと迎への人々が来ている。その一行を従へてゆる/\と歩くのが普通の家元らしい形式ではあるが、私は先方に負担をかけるのを考へて誰も随行の人をつれて行かなかった。そして自分でトランクをかついだ。どうも、迎へに来てゐる年寄りにそれを持って貰う気になれない。それは、土地の人々にとって物足りなく感ぜられたかも知れない。
とにかく、花道について云っても、花を「立てる」と云はれた立華にはスタイリスト的なものがある。しかし、一方がさうなっていく時に、その反対のものが現れるのも自然な姿である。この時に「いけ花」又は「なげ入」の風が起ったのであって、さうした二つの形は、季節の移りと同じ様に人間の世にも現れるのである。然し、世間は不思議なもので、一度び起った投入の風も、いつかはスタイリスト的なものとなってゆく。近代の挿花にもその傾向がないとは云へない。それよりも、自然の景観を素朴に見る心があり、それは、単に自然の風趣を考へると云うよりも、他に対する素朴なる思いやりを伴ってゐるのである。
○
先日も、私の社中の研究会があった。ふだんの稽古場を離れ、野外の花をとって自由に花を挿す試みであるから、云はゞ俳句の吟行に等しい。所が、生けられてある花を見ると、稽古場の花と少しも変りがない。それを私は快く思はなかった。自然苦言を呈したのであるが、その後に生けられた花を見ると、あり合せのものを利用した可成り面白いものがあった。詰り、指導の方針次第で、如何様にもなるのである。スタイリスト的に物を考へるのを離れ、自由に自然を生かす喜びを感じなければならない。
この夏の北海道の旅行の時にも、その土地の人に云ったのだが、自らの土地に面白い草木があるに、それを用いるよりも、花屋にある花を用いねばならない様に思っている。東京やその他の都会の人が喜ぶ類の花が送られて来て、新鮮な精気を失ってゐるに拘らず、それを用いることが花道である様に思っている。この人々に私は云った。都会にある人は、自ら山野を歩いて草木を採取すべきであり乍ら、それが自由に出来ないために、店に売っているものを用いる。然し、広き野の中に住んでいる人が、その真似をするのは当らない。それよりも、身に近きものを用い、それを新鮮に生かすことに道がある。
実際の例を云ふと、北海道にも、又その他の日本の国土にも自然に生えてゐるものに、かのギシギシがある。これは、夏の草が未だ青いうちにも枯れゆくもので、その葉や茎は、枯れゆく時に特殊の色彩を示す。咲く花の様な美しさでなくとも、自然の野に出来ているものが、他に先だって枯れる色彩を現すのは、季節を感ずる心からも面白い。それと、未だ青い他の草とを取合はせると、自然な野の感じが味へる。私は、講演会の席に、これをとって来て、かうすれば現にうつくしいではないかと云った。それを見て「成程そうですね」と土地の人も云ってゐた。従来のスタイルに捕はれない物の見方がその人々にも了解されたのである。それで、「長く村史にとゞめて…」とその時の挨拶に司会者は、云っていたのであるが、これを御世辞ではなく、心から出るものとして私は聴くことが出来た。
この北海道は、他の土地に比べて花が特に盛んである。遠き原野を想像し、寒い冬を思う時に、この土地に挿花が盛んに行はれているのを人は不思議に思うであらう。けれども、あまりに豊かな土地よりも、むしろ乏しきにあって、人々は美しいものに、より多い感銘をもつのである。
○
この北海道の旅行で、小原流の門弟としては最も古い羽田老人に会った。既に七十を過ぎる高齢で、初代雲心時代の弟子である。この人が壮年時代に、遥々大阪に出て来たのは小原流盛花の初期で、遥々北海道の人が雲心に会見を求めたのは、羽田氏その人よりも、雲心自身にとって感銘すべきことであった。以後今日に至っているのであるが、この人は既に老齢である上に脚が悪い。それで、日常は家の外にあまり出ない。それが、今度の私の旅行をきいて、遥々と駅まで出迎へてくれた。家元と地方にゐる教授と云う関係よりも、恰も親子と云う様な情があるのを私は感じた。近代挿花の色々な写真を見せたら、私はわからんが、油絵みたいなものを取容れて研究せんならんのやなあと云っていた。二日半程の滞在のうち、その写真をためつすかしつして見ていた。七十いくつになるのに、その態度は恰も花道の虫と云った様なものであると思はれた。一歩でも前進したいと云う心持が止み難いのである。これには激励された。殊に若い娘さんの弟子を顧み、ヂッチャッン(爺さん)にはわからんので、家元によくきいて、それをヂッチャンに教へてくれと云っているのは、いとしさに似る情があった。
○
花は、雑草一本でもよい。ピンときくかきかんかにある。デカくしたのはいけない。
昔はイキとかスイと云ふ言葉があったが、近代はその影をひそめている。その代り今の時代に合う言葉もない。
○
私は、思ひついたことに体当り的に突込んでゆく性格である。それで、ある友人は、「お前は物を噛まない」と云った。珍しいものを口にすると、それをウノミにすると云うのだが、私に云はすと、アンマリかみしめてゐると香気が消えると思う。その消えないまゝで、ズバッとやってのけるのが私らしい主張だ。
世の中には、いつも柳の下にドジョウは居ない。ドジョウは見た時に、すぐつかまねばならない。
いけ花の芸術は、永久にその作品がのこるのではない。それでチャンスに打って出る性格が自然に必要である。練りに練ってその作品を出しても、大衆が次の魅力を求める様になっていては、おいしい御馳走も意味がない。それで私は不意打戦法でゆく。さう云うことをするには、日頃に、それが出来る様な台所の準備が出来ていなければならない。ソレと云へば、台所にいつもお湯がわいていて、そこに持込んできた材料をすぐ料理して出せるようになつていなければならない。
踊の名人は、場へ出る時のみでなく、いつも練習を怠らない。又職業野球でホームランを打つ人は、いつも練習しているからうてるので、毎日毎日練習してゐなければ結局飛ばない。これは、芸術であらうが、スポーツであらうが変らない鉄則である。
私は、第一球をねらう方で、選球せんたちだ。
○
この性格と関連して自分でも不思議なのは、何か意見をいうにも、大勢の人の顔を見ないと、どうも調子が出ないことだ。あとから、結構な話でしたと云はれることがあるが、自分でどんな事を話したのか思い出せん。
○
故西川一草亭は、大正の末から昭和にかけて大きい足跡を遺した花道人であった。例の「牡丹切って一草亭をまつ日かな」の句を夏目漱石が作ったのは、この人の名を世に高からしめているが、それよりも、世の多くの芸術家や財界人とも交り、それらに伍す位置を示したのは、新しい驚きを世に与えた。他の花道家との交りはなく、云はゞ別格のようなものであったが、それでいて花道そのものゝ位置を社会的に定めた功績は大きい。
その花展は、京阪神の大邸宅をかりてよく行はれたが、百貨店を用いて行はれる花展とは別の趣きのものであった。その行き方は、今日に行はれている新しい花の創作というよりも、いけ花の中に流れてゐる精神をつかみ、それを新しい時代の生活に生かさうとしたものである。又、これによって、いけ花の趣味を深めて味はせる役割を果した。さう云ふ精神的意味でいけ花を普及した人であった。
この西川氏の活動があった時、その反面に、吾々は、作品としての新しい花の研究をすゝめていたのである。何れにしても、その仕事は、現代花道の動きにとって大きいプラスであった。近世にあってはとにかく西川さんである。
その西川一草亭さんがなくなった時は、未だ二代の在世中であったが、私はその意をうけて弔意を表しに京都までいった。生前に直接の交際があったわけではないが、その死を悼んで態々弔意を表したのである。その時も、あれだけ社会的に活動していた人であるから、葬式は定めて盛大なものであらうと予想していたが、家の中に這入ると、何も特別のものはなく、床の間には、故人の絶筆であった「風流之人」といふ一行がかゝり、それに、白いアマリリスの花が僅かに手向けられていたのみである。葬儀の形式も、普通のお焼香ではなく、一輪の花を霊前に捧げる方法であった。会葬の人々は、新しい手桶の中に入れられている花の中から、一つの枝を選び、それを霊前に捧げるのだが、その手桶の中に、水々しく浸ってゐた青い葉の色が今も私に思い出される。お焼香ではなく、一輪の花を霊前に捧げる方法であった。会葬の人々は、新しい手桶の中に入れられている花の中から、一つの枝を選び、それを霊前に捧げるのだが、その手桶の中に、水々しく浸ってゐた青い葉の色が今も私に思い出される。
○
先日名古屋にいって一泊した時、相当年配の女の人が給仕をしてくれたが、話のついでに、今日は私の踊を見て貰いませうという事になった。それを見ると如何にもうまい。それに感心して旅の一夜を心持よく過したのだが、後できくと、その人が長吉ねえさんと云って西川流の名手であることがわかった。私はそんなことは知らなかったが、何れの道でも、一つの芸に撤した心持には感銘をうける。後でもその人に会って、色々の話をきいたが、こんな話をした。或時一寸外出した所、知った人に会って、これから信貴山参りをするので、一緒に来ないかと誘はれた。因よりそんな心持で外に出たのではないが、とにかく行くことになって、信貴山参りをしたが、帰りに一寸寄っていかうというので、大阪の南地へいった。そこで、踊を見せて呉れとの事になったが、今日は練習をしていないので骨がかたくなっているからと辞退したと云う。名だたるその道の人であるので、何時でも踊ってよいわけであるが、細い所に気をつけてゐるその気質に私は感心した。
と云い乍らも、是非にと云はれて、他人の衣裳をかりて踊ったというが、その南地で思い出すのは、富田屋の八千代という名妓がいたことである。少し年配の人ならその嬌名を記憶してゐるであらうが、この八千代には、有名にもなるだけ、他の人とは違った心得があった。譬へば他の芸者であれば、人力車などに乗って外に出る時、如何にも澄した顔をしているのが普通であるが、この人は「あれが八千代だ」と町の人から云はれる時、俥の上から、会釈をして通ったという。それは容易に出来るようで出来ない素直な心である。この心持が、自ら高しとするよりも、自然に他からその名をうたはれる原因であった。
この八千代が後に菅楯彦氏の夫人になったのは有名な話でめる。その菅氏にも私はある席であったが、人間として如何にも温い感じがする人であった。
この菅氏の夫人になった八千代も今は亡き人になったが、その死ぬ時には、菅氏に遺言して、「死顔を決して人に見せて下さいますな」と云ったという。世に美しさを謳はれた人の最後の言葉として、流石に艶深い。
歌舞伎の話
今の世間の考へからは、それを古いと云うかも知れないが、私は歌舞伎の世界に現れてくる人間の味はいに深いものを感じる。私の父も、芸にたづさはる身として、この歌舞伎を愛好していた。それで、子供の時分からよくつれられて見にいったものだが、芸のカン所になると、コゝダといふ風に、肱で私の方を突いてくれた。さう云う風で、この歌舞伎の味はいはよく私の身に泌みている。
今も覚えているのは、中車の仁木弾正の如何にも憎々しい演出である。その芸を見てフルイアガル思いがした。これを見た時には思出話があって、私は妹と共に大阪から京都の南座に見にいった。実際は内證で見にいったのであった。所が後でそれがわかって仕舞った。すると、内證でいったのではないといふ風に事をつくろはなければならない。それで、私は、翌日まだ暗いうちに起きて、再び京都までゆき、帰りに買ってきたのだと云って出すお土産を整へた。
とにかく、そんな風にして、歌舞伎の世界にひたるのが好きであったが、この頃の人には、さうした世界が忘れられてゆくと共に、昔の様ないゝ役者も居なくなる。菊五郎も亡くなったが、一度これらの人がなくなると、再び次の人が出るのが困難になるであらう。修錬された芸は仲々生れるものではない。昔の人は、芸について並々ならぬ修錬をしたが、一方から云うと、社会がその様に修錬されたものに親しみ、それを見る眼をもっていたからである。けれども、今の社会は、修錬された人間を見る眼を段々失ってゆく様に思はれる。以前の時代には、歌舞伎の中に現れる人間に感銘をもち、そのよさが、日常の生活にも眼に見えない作用をしていたが、今の時代には、それが失はれてゆく。
さうは云うものゝ外国映画で今上演されている「しのび泣き」は好いと云う話をきいた。後にむいた背の表情で、哀愁の気持が現はされている場面があるさうだ。それなどは、歌舞伎に見る表現に似通う所がある。歌舞伎は古典芸術で、吾国の義理人情の世界を現してゐる以外、単純化され、凝集された表現に魅力がある。それとは異り、たゞ華やかなものに赴く傾向が何時の時代にもあったであらうが、その中に、この歌舞伎とも云はれる表現法が現はれて来、それに人々が感銘するのを私は面白いと思う。
古いとか新しいとかの徒らなる概念を人はもつが、真実にその内容となって動いてゐるものを見ると、不易なるものゝ隠顕がある。
歌舞伎の話に戻ると、私が大阪でよく食事にいく所がある。そこは歌舞伎座の近くなので、この道の人もきていて、そこでこんな話を聴いた。忠臣蔵の判官切腹の場面の時、後から出てくる由良之助は、静かに判官の手の短刀をとり、肩衣を直して平伏するのが一つの型になっているが、その肩衣は、死の表情を現すために、最初は、乱れた姿となっている。それを、後から直す所に型があるのだが、そのことを予想して、役者は姿直しが出来る様に、着付をゆるくし、腹をひつこめて伏してゐるのが普通の心得である。けれども、関西にきてその役を演じた所、一向それを直してくれない。それで、さう云う型もあるのかと思つたとの話であつた。それは、今までに修錬された芸が、新しい時代に忘れられていく例である。切腹した主人の前に現れた臣下が、乱れたその肩衣を直す心遣いは、僅かな行いではあるが、云い知れぬ感銘を与へるものである。これを見ている人にも、ホロリとしたものを与える場面である。さうした事は、別に歌舞伎の型としてゞはなく、実際の人間も、かゝる心遣いを持たうとしていた事によるのであるが、そこに心持があるのを時代が忘れんとしているのが、さうした型をも忘却することになる。
所で、その型を忘れた話以外、同じ場合の河内屋の話をしていた。河内屋は、手にしていた短刀をとる時、その手をナムアミダブ/\と云ってもみ、又乱れていた肩衣をシャンと直したのであるが、それをした後、又、後から戻ってきて短刀を持ってゐた手をナムアミダと云って再びもみ乍ら、親ユビを人指ユビと中ユビとの間に一寸はさました。これは勿論悪戯ではあるが、それだけの余裕があって、芸をしているのには、別の意味で感心させられたとの事である。
詰り、種々の心遣いをし、それが人に感銘を与えるのも、所詮はかゝる心の余裕に出るのではあるまいか。
今の話から想はれるのは、昔々の花を生ける道にも、それと同じ事があることである。以前の時代にあつた様な芸の修行という心持は花を生ける道にも段々失はれてゆきつゝある。今、御影の家には内弟子がいるが、これなども稽古日にきて習つて帰る人の様に、自分もしたいらしい。けれども私は花を運んだりしている中に、本当の修行が生れるのであると云つている。花を習ひにくる人は、云はゞお客さんである。これに比ベ、種種の雑事をしているのは、一見修行から遠い様に思はれ乍ら、実は、その状態から生れる気甲斐性に最も尊い所がある。真の修行は、他から教へられる事でなく、この気甲斐性を根底とするものでなければならない。それをたゝき出す所に、以前の修行の尊い所がある。
利休について聴いた話では、実子の道安に最初から茶を教へようとしなかつた。それで、ある日に道安が父に向ひ、茶を教へて賜はれと云ったが、利休はそれに答へず、少庵に習へと云った。少庵と云うのは、継母の連子である。この答へを聴いて、道安は、少庵には習い候まじとの決心を明らかにした。それを聴いて利休は、初めて茶を教へたというが、それは私の云う気甲斐性を尊ぶのである。
さう云ふ点では、昔からの生活を護ってゐる人によい所がある。私がよくいく嵯峨のKと云う料亭に「お愛さん」という女中さんがいるが、この間こんな事があった。最初着いた時に、床の間に花が生けてあって、それは紫苑を扱ったものであったが、風呂から上ってくると、これに露が打ってあった。風呂上りのスガ/\しい心持と、露をもつ青い葉は如何にも好もしかった。これも、今云う気甲斐性からするのであって、心の中にある眼に見えない気が、何等かの行いをさせるのである。それが目立たないまゝに人の心に深く触れてゆく。この人々は、芸の修行をしているのではないが、自分の仕事に気を入れてすることが、色々の行いとなり、そこに感謝すべきうつくしさが現れる。
吉兆の料理
今は発展して大きくなったが、大阪には吉兆といふ料理店があって、最初は狹い所で営業をしていた。主人が料理に趣味をもち、所謂気を入れた料理を出す店として人に知られている。
その吉兆の話だが、主人の言葉をきくと、結局東京ではダメだろうと云ふ。
材料がよくないからである。野菜などは京都一園で出来たものが特によいが、東京では気のきいたことを仕様としても出来にくい。それは、長い歴史の間に自然に洗錬されたものが関西にはあるからで、文化の新しい所では、それを仕様としても結局出来ないという。芝居の雁治郎が関西の名優であった様に、それを他で真似しようとしても結局出来ない。
これは、私のうちでの話だが、正月には流内の主だった人をよぷ。その時には大阪から吉兆の板場がくるが、客が多いので、汁でも何でも沢山つくっておけばよいと思うが、一座の客が十三人であると、十三人づゝそれをつくる。その調子では客がつかへるので、一緒に澤山つくったらというが、ヘエと云ひながらそれをやらん。初め味噌を濃くしておいて人数がふえたら薄くするということをやらん。文さんと云う若い板場だがそう云う所をしこまれてゐるのであらう。どの世界でもさうした修業がなければ駄目である。この修業は結局自分のすることに自信をもつことである。それだけの苦心がわかる人であらうとなからうと、吉兆というものである限りはそれをするのが尊い。他の世界でもそれと同じことがなければいけない。
又、この吉兆の料理について云うと、出来上ったものを盛込むのに、芸の感覚がある。それは、一つの材料と他の材料を取合せる時の「間(マ)」と云ったもので、二つのものゝ間のイキの通ひである。この点は、花を生ける吾々にとっては、最も敏感に感受せられるのであるが、云う所をきくと、一つのものを盛りかけて、その間に気が切れるとあかんという。五ツなら五ツ盛つても、呼吸が続かんと同じようにいかんと云ふ。見てゐるとチヤツチヤツと手早くやっているが、その間にイキが切れない様にする句が一つの芸なのだ。吾々が花を生けても、一本一本がバラ/\でなく、連つてなければならないが、この料理の盛込を見てゐて成程と思う所がある。
今年の正月には、柳に餅花をつけたのを料理に用いた。白い餅皮にウニをつめて柳につけ、別に焼鳥や玉子焼などを通して、三宝の上の俵につきさし、それを八寸かはりに持って出て取りわけるのであるが、この柳に餅花をつけるのは、花道家の領域にも入るので、吾々としてもやって見るのだが、自分がやると線のうつくしさを考へるのでどうもお花の様になる。それでは、食物としての感じがなくなるとこの板場はいう。これは仲々吼興味あることであった。柳の枝に花をつけるのに美的な心持があるのは必要であるが、食物としての心持が起るか起らないかは又別の問題である吾々とは違って、この人々は、それを食べたいという心持が起る様な美を考へているのである。同じ料理人であっても、それを若い者がすると、ドウモかさ/\とした感じになる。所が文さんというその人がやると、取って食へるという様な感じになる。私等がやると飾り物と云う心持になるのだが、これは、その道によって根本精神が異っているからである。ムツカシイものだと思ったが、そのムツカシイ中に成程と思う所がある。文さんが先生一つやって見なさいというのでやつて見たが、ドウモ食べたいと思ふ様に、その餅花は俵につけられなかった。
吾々は始終こう云う所から教へられている。それを味い乍ら、一箸一箸食べていると、私は私の道に一生懸命にやらんならんという気持になる。だから家族にも云っているのだが、私はゼイタクで吉兆の料理に親しむのではない。楽しくもあり、又勉強にもなるからである。それ/\の道の苦労は楽しいものだ。それでなければ芸は生れてこない。
物としての価値ではなく、それに如何なる心がこもってゐるかを喜ばなくてはならない。けれども、さう云う心持は段々少くなってゆく。卒直に云へば、今日の新興の人々には本当の心をこめた親切がわからない。これは不仕合せなことである。小さい事が大きいことに発展するのだから、眼に見えない親切が何事にもあるのが必要である。
*小原家では正月の客人用に用意する懐石料理は、「吉兆」に自宅まで出張してつくってもらっていたという。まだ若かった湯木貞一氏が一番弟子の中谷文夫氏をともなって器を用意し、料理にかかる姿を家族は尊敬の目でながめていた。『胸いっぱいの打ち明け話』小原稚子1981 p90
植物の芸術
七星会の第一回展に、竹の幹や柿の若葉を扱った作品を出す以前、私は陶芸家の宇野氏や洋画家の吉原治良氏などと共に、京都にある桃山時代の障屏画をよく見て歩いた。その時の印象がテーマになってあの作品が出来た。
その中でも、天球院の襖絵は今でもよく覚えてゐる。這入った所には、爛漫とさく朝顔やてっせん蔓を画いたのがある。真中の所には竹に虎の絵があるが、それを見ると、青い竹の肌から皮がおちかゝつてゐる。それを見て私は感心した。竹が青く艶々しく成長し正に皮を落さうとしてゐる感覚は、花道家としても見逃せない。この竹と共に虎がかゝれているが、それは、親虎が子を愛育してゐる図で、成長しかゝつた子の虎を愛情ある眼で見てゐる図である。その背景に、正に皮を落さうとする若竹がかゝれてゐるのは共に通ふ心持である。寺僧によると、この絵は山楽の筆になるもので、石田三成がその父の菩提のために、寺をたてた時、その余りの材料で作ったとの事である。何れにしても、信長秀吉の時代の空気が現れ、猛虎が子を育てる図は、その時代の逞しい心持に添うものである。当時の武将と云へば、猛虎の様に思うかも知れない。けれども、その虎には若き子を育てる愛情があった。
とにかく、その事情と共に、若い竹が正に皮を落さうとしてゐる図を見ると、新鮮な意志が伝わってくる。これを中心にし、方丈の向って左には、梅をかいた図があるが、これを見ると、その枝の上には、小鳥が一匹とまっている。しかし、右側の朝顔をかいた図には、動物は何もかゝれていない。中央には、今云う様に、猛虎がいるが、その左右のものには、動物が漸次省略され、遂に植物のみの世界となっている。この動物がゐない植物のみの世界に、花道家としての私は眼を見張るのである。
以前は、花鳥画が云はれていた。草木に動物を書き加へたのがこの花鳥画で、所謂院体の絵の中には、この類のものが多い。その動物を去って植物を主に見る傾向が現れたのは面白い。
智積院の襖絵を見ても、この植物のみの世界がかゝれてゐる。その筆者である長谷川等伯は、利休の肖像をかいてゐる様に、堺の民衆との交渉があって、今に遺ってゐる「等伯画説」を見ても、堺の人がジズカなる絵を喜ぶを記してゐるが、一般に豪華なものを喜ぶこの時代に、ジズカなものを更に考へてゐたのは、植物のみを材料とした絵が現れる理由で、それは社会的に云へば、大衆の意に相応するものであったのであらう。
考へようによっては、当時の民衆は植物的なものである。それが、動物的なものと共にあったのが武土社会であるが、この動物が段々いなくなる世界の靜かさは、確に、民衆の願いであったに違いない。
私は、これらの絵画を見て、七星会の第一回作品を試みたわけで、その作品にも、孟宗の竹が青い肌を見せてゐるのを数本つかひ、これに柿の枝を配した。いけ花の方法でも、安土桃山の時代の作品にある心組みを生かしうると思ったからである。しかしこれをいけ花の世界にうつすについては技巧的に省略が必要である。大きい作品の場合は特に省略が必要で、孟宗の竹を用いるについても、特にこれに意を払った。若し、まともに直立する様にこれを扱へば、五月の松山の様になる。しかし、その間の間隔に心をつけると、これに動的な表現が感ぜられる。とにかく、植物のみの世界を表現する時には、単純化されたものがその中になければならない。
そこで思うに、自分が感心するのは、同じく安土桃山の時代の作品と云はれるものの中にあっても、山楽又は等伯のものである。一般に安土桃山時代の作家として知られてゐる中には永徳があるが、私は永徳は嫌ひである。永徳は、民衆的な心持が巷に流れた秀吉時代よりも、それ以前の精紳をもっている。それを嫌ひと云うのは、リアルな感銘に対して古い感じがするからである。絵画としての歴史的な立場とか、画工として狩野家の伝統をよく生かしてゐるのは結構であるが、それを好ましく思はないのは、花道家すぎる見界からである。とにかく、吾々の仕事と結びつき、その胸をうつものが永徳の作にはない。それが、山楽等伯となると吾々に接近してくる。おこがましく云へば、等伯山楽を見ると自分等の種本の様な気がする。そこから作品のテーマが引出され、これに魅力を感ずる。
この永徳的なものとしては、以前の挿花に、曝木のボクを用いることがある。それは、狩野派の絵にある心持とも合うが、私はそれを好かない。その反対に、智積院で、ススキに芙蓉が配されてゐる絵を見てドキツトした。詰り、植物的現実感を尊び、観念的なものを嫌うのである。
花の取合せについて云うと、林丘寺にある図が面白い。こゝは後水尾天皇の皇女である方が尼となって居られた所で、父君の天皇が花の道を好まれた方なので、その趣味が伝ってゐるのであるが、こゝに遺されてゐるいけ花の図を見ると、その取合せに近代感覚がよく現れてゐる。特にそれが女性的であるのがうつくしい。河骨にフトイを取合せたのなども、自然描写がよく現れてゐる。後水尾天皇の皇女でもあり乍ら、尼としての生活をおくられたのは、徳川幕府の封建社会的な規制とは離れた面に立つことで、この立場にあって、自然への心を細くもっていられたのは、安土桃山時代のものを見るとは違った感銘がある。殊に女性としての優しい心情が現れ、一面装飾的ともなりつゝ、その取合せに特別の感覚があるのは見逃されない。
この取合せは、かの花鳥画の時には、動植物の間に注がれ、その後、植物のみの世界に解放されたとは云へ、再び、徳川の社会となる時には起って来なければならない感情であるが、林丘寺の女性によって示されたのを見ると、その周囲をうつくしく澄みきった愛情で見る心に包まれてゐる。譬へば、水中に深く葉を沈めた河骨と、細く直ぐやかにのびてゐるフトイが取合されているのなどは、新しく植物的なものの中に含められた情念である。事実、水中に葉を沈めてぬる河骨の様な生活が、日常のものであったかも知れないが、それとは別に、空気中に細く直ぐやかにのび出るものへの思ひもあったであらう。それは、安土桃山時代の植物の世界のように、逞しい行動力を伴ってゐるのではない。うつくしい情念として描かれているにすぎないが、その故に装飾的なものともなる一面がある。しかし、、精しくその図を見ると、この模様的な設計にのみ安住してゐるのではなかった。中には、今のカンナ、当時ダンドクと云ったものも用いてゐる。果敢なげな植物にのみ心をとめているのではなかったからである。