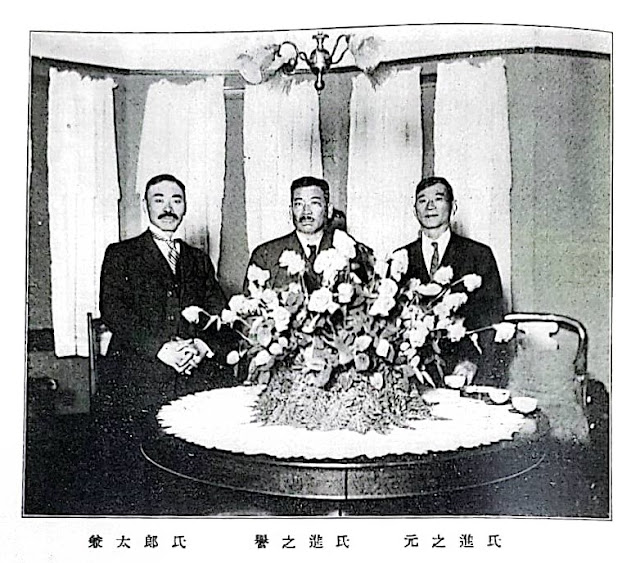将軍に付き従い室町文化をリードした「同朋衆」とはどんな人たちだったのか 同朋衆と時宗
○ 『武家文化と同朋衆:生活文化史論』 村井康彦 筑摩書房 2020年
室町時代は、足利将軍家15代、250年の歴史がある。14世紀の前半から16世紀の後半までという長い期間、南北朝の分裂を収めたものの各地の守護大名の動向に気を配りながらの運営で、どの将軍の時代にも常に敵がいた。将軍の権威が弱かった、と言われる。後期には家臣に暗殺されるなど混乱を極め、10年におよぶ応仁の乱は京都の街を焼き尽くし、戦国時代の幕を開いた。こうした波乱の時代にあって、サムライのトップである将軍が、歌を詠み猿楽を愉しむような「公家化」が目立つのは、ひとつには天皇、朝廷の力を幕府に近付けようという策略もあったと言われている。同朋衆は将軍の側についてよく働いた。
同朋衆はどこからやってきたのか
同朋衆という名称が現れるのは、足利尊氏のあとを継いだ2代義詮(よしあきら・在職1359〜1367)の時代だったという(1358年の記録)。少なくともそれ以前には同朋衆は存在した。その後、室町幕府の体制が確立していくなかで職制が整備、拡充され、東山文化をつくりあげた義政の時代にピークを迎える。最終的には、戦国の世となるにしたがって将軍の権威失墜、将軍家で蒐集してきたお宝、「東山御物(ごもつ)」の流出などが重なり、これらに付随していた同朋衆の存在意義、役割が衰退していった、ということである。
同朋衆の源流は、時宗の僧侶、信徒(時衆)である、という。「法体で阿弥号を持つ」という絶対条件は時衆と重なっている。時宗は一遍上人により、1275年に始められた。法然・親鸞の始めた浄土教の流れをくみ、踊り念仏によってすべての人が救われると説き、各地を布教して回った。公家、国家のための仏教から武家、民衆のために起きた鎌倉仏教のひとつとされ、地方の武士や農民に広まっていた。
時宗は、早くから葬送に関わり、野辺に遺棄された遺体を埋葬し供養していた。こうしたことから戦に出る武士との間に深い関わりができていた。「同朋同行」という仏教用語が同朋衆の名前のもとになったという説があるように、時衆は武士に付き従って、戦場に赴くことも珍しくなかったという。時衆は僧兵のように武器を持って戦うことはしなかったが、「金瘡(きんそう・刀による傷)」の治療に長けており、危険な戦地に同行し、傷ついたものの治療と亡くなった人の看取り、埋葬、供養を行った。兵士に最期まで従ってその死を看取る。現代なら「衛生兵」と牧師の両方を担ったわけで、大切にされないはずがなかった。当時につくられた軍記には「トモニツレタル遁世者」「最期マデ付タル時衆ノ徒」などと記された。武士からすれば、死後の救済、極楽浄土行きの保証をしてくれるわけで、戦死することの恐怖を少しでも慰める存在であった。特に地位の高い武士には信頼できる同朋衆が常に身近にいただろう。彼らの中には戦時の緊張を慰めるために和歌を詠み、歌い踊るものもおり、そういう文芸と芸能に長けたものも少なくなかったようだ。こうして戦時だけでなく、平時にもそばに置きさまざまな用事を手伝う同朋衆の初期の姿となった。
同朋衆の初期の供給源が時衆だったとしても、いつまでもそれがそのままとは限らない。時宗信徒でないものも存在していた。ただ、身分の低いものが高い地位者と接する際に剃髪し法体となることによって現世の身分から無縁という意味でそれぞれが阿弥号を名乗るようになったようだ。間違いやすいことだが、「同朋衆は必ず法体で、阿弥を名乗った」というが、「その逆はかならずしも真ならず」で、僧侶の姿だから同朋衆であるとか、阿弥の名があるから、同朋衆であるわけではない。同朋衆とは別な座的な結びつきのなかで生活した猿楽の名人、観阿弥や世阿弥、音阿弥のように阿弥を名乗りながら、時宗の信徒ではなく、同朋衆でもないというものも存在した。たて花で知られた文阿弥・宣阿弥・正阿弥も、時衆ではあったものの、同朋衆ではなかった。歴史に名を残す築庭家、善阿弥も足利義政に重用されたが同朋衆ではなかった。
将軍の同朋衆にあって、たて花を得意とした者に「立阿弥(りゅうあみ)」がいた。立阿弥は義教から義政まで3代に仕えた名人。この名前は職掌の名ともなり、何代かに渡ってその名前が引き継がれ、花を立てていたという。義政の時代には、台阿弥(たいあみ)という人物も花をよく立てた。ほかにも葉阿弥という人の名も出てくる。
立阿弥は「御会所の同朋(衆)」と称されており、座敷飾りの重要な要素としての花を立てたが、花は座敷飾りの一要素でしかなかった、とも見て取れる。「唐物奉行」を務めた能阿弥(義教時代)、芸阿弥・相阿弥(義政時代)の三代三阿弥や同時代(能阿弥の先輩である)の千阿弥、立阿弥らは、みな唐物の書画・器物にそうとうな知識があり、取扱いも熟知していたはずであり、花を立てることもできたかもしれない。同朋衆は、将軍が招かれた先の座敷飾りも担当することがあったという。将軍を迎える側はその名誉を受けて饗応を用意するのだが、その後に多くの客を招く催しに合わせて将軍家自慢の唐物を見せることで将軍の威光が示された。同朋衆はいわばクリエイティブ・ディレクターとして将軍の権威発揚を代表する重要な仕事を担っていた。
たて花について、座敷飾りに必須の三具足の花は「真」であり、書院の花は「行」、違棚の花は「草」というふうに形式が整えられた(真、行、草はのちの「いけばな」に影響、展開される)。いずれにしても花は座敷飾りの中核、最重要要素であり、この座敷飾りの場において「たて花」は鍛えられていった。
同朋衆の時代(会所、座敷飾り、唐物、たて花)
同朋衆の初期には文芸・芸能に長けた時衆から始まったと目されるが、室町幕府の体制がしっかりとするにつれて、足利将軍の側にあってはその文化活動の高度な知識と技能を持った担い手として力を持つようになっていく。たとえば「唐物奉行」は、当時、中国(明)からおびただしい量の書画・器物等が輸入されており、その価値を判断する目利きであり、将軍の蒐集を手伝い、また管理をするといった高度な仕事を担っていた。「取次」の仕事も大勢の臣下や関係者から贈られる中元などの贈り物の仲介や目利きをしていたと思われる。
同朋衆には、文芸、音楽、茶や花、造庭など、それぞれ、さまざまな得意分野があったわけだが、彼らが互いに関わりながら仕事に従っていた「場」に注目することが大事だと村井氏は指摘する。その「場」とは「会所」である。会所は室町幕府、とくに将軍の推進した諸行事の場として発展したもので、文字通り人々の集う場所だ。室町文化の心臓部とも言えるこの部屋や建物は、会所としてふさわしい構造を持った建築様式として完成する。それが「書院造(しょいんづくり)」と言われる様式だ。この様式が現代に至るまで続く日本の生活様式の原型となった。
著者は、書院造のスタイルだけを見るのではなく、会所という「場」を研究すべきだと述べている。鎌倉幕府の衰退から南北朝の60年におよぶ混乱を収めた3代足利義満の時代以降、幕府が京都に置かれたため、「武家の公家化」の機運が起きる。この機運によってさまざまな文芸や芸能が将軍家や公家で行われるようになるのだが、将軍家の用意した専用の場所が「会所」というわけだ。「会所は遊興の場所のことである。それが南北朝=室町初期の武家邸宅に出現、発展し、武家文化ひいては室町(前期)文化のシンボルとなった」(『武家文化と同朋衆』村井)。会所はのちの茶室とは異なり、和歌・連歌、舞楽、猿楽、白拍子などを催し、あるいは唐物の書画、器物や花を並べて鑑賞し、茶を飲むというふうに多目的、複合的に利用された。花は床飾りの中心をなす三具足(花瓶、香炉、燭台)の一つとして立てられるもので、座敷飾りの一構成要素として存在していた(座敷から出て単独で自由に鑑賞されるようになってはじめて「立花(りっか)」となる)。
会所で行われた花の催しについては、義満が開催した「花御会」というのがある。この会は花という文字はあるものの、実質は花器の品評会であり、各人が持参の唐物の花瓶の優劣を競う遊びだったという。最初は花というよりも唐物への関心から始まったということが興味深い。今回は詳しく触れないが、鎌倉末から室町時代の「たて花」は、宮廷・公家の関係者(雑掌・大沢久守や僧侶の花)の流れと将軍家、同朋衆(立阿弥ら)が座敷飾りの構成要素として「法式」を確立する流れのふたつがあって、それらが戦国時代をへて池坊に集約されていくという物語となっている。茶の湯もいけばなも「会所という場・枠から脱却するところに、本格的な成立があったということである。それがとりもなおさず茶道や花道成立の第一歩であった」(前掲書、村井)。
まとめると室町時代は、供花の時代から、鑑賞の花、室内装飾へと形式(「真」「行」「草」)が整えられる時代だった。(1)「たて花」→(2)法式を定めた「たて花」および、茶室の花=「なげいれ花」→(3)たて花から「立花(りっか)」へ(一方の「なげいれ花」は江戸期に「抛入花」へ)という流れとなる。
北山文化、東山文化と言われるように室町時代に規式が定まった芸能諸分野では行事の記録や各種御飾書といった記録・マニュアルが制作された。能阿弥・相阿弥2代によって完成された『君台観左右帳記』(将軍楼台の左右の飾りについて記したもの、1476年~1511年ごろ)を始め、茶の湯では数多くの茶会記が、花の世界では「花伝書」が制作され今日まで伝えられている。花伝書はすでに15世紀の後半あたりから現れはじめており、初期のものは絵でパターンを見せる図鑑的な性格が強かったが、16世紀に入ると、池坊を中心にたて花の構成理論はもとより、理念ともいうべきものが生まれた(『専応口伝』1542の「花論」など)。とくに室町後期、天文年間(1532~1555年)に集中しており、「天文文化」と呼ぶこともあるそうだ。こうした茶会記や花伝書の登場は、理論・理念の形成を示すとともに、さまざまな階層の人々に量的に広がっていく転機、メルクマールとなった、と著者は指摘している。実際、この時期の花伝書には転居の花、婚礼の花など生活習俗に根ざした花の立て方が中心として書かれているという。これはまさに、立花が市民層まで普及していったことを物語っている。七夕に開かれる花会は公家、地下侍、寺庵らが前日から花瓶を持ち寄って豪華な花を競い、それを見物する人が後をたたない盛況ぶりだった。当初、花伝書は「秘事口伝」、門外不出の秘書であったが、江戸時代には「花書」として出版され、多数の流派を経て広く知られるようになる。
室町以前の花(供花の変化)
ここで、一度、室町以前の花がどのように扱われていたか、絵巻に描かれたものを見ておくことにしたい。ここで見たいのは、書院造の座敷飾りへと整えられる以前の「床の間」の様子である。特に「押板(おしいた)」の場に注目したい。押板はもともと仏画などを壁に掛け、その前に三具足(香炉、燭台、供花)などを供えるための板を置いたことに始まる、プラットフォーム、結界のような場だった。これが室町時代に建築の一部として造りつけられるようになる。当時の家屋は板の間が主体で、人が座住する場所にのみ畳を敷いた。
図1は鎌倉時代末期(1309年)の『春日権現記』、図2~5は室町以前、南北朝時代(14世紀の半ばから末まで)に描かれた『慕帰絵詞』で、「床の間」の出現を示唆している。
図1 鎌倉時代末期の絵巻に描かれた座敷 床の間はなく、花(ここでは紅葉したカエデ)は座敷の隅に置かれている。『春日権現記』(画像は国立国会図書館デジタルコレクションから)
まず図1(鎌倉末期)だが、花瓶には紅葉した大ぶりのカエデがひと枝いけられている。なにか技巧をつくしたといういけかたではなく、さりげなく花器に入れてあるように見える。花器は部屋の隅の畳の上に直に置かれている。この当時の「畳」は、居間であるとか、お客さんが来たときに敷くような使われ方をしていた。普段は立て掛けて置かれていたらしい。絵に描かれた部屋は畳が敷き詰められている。畳のへりは「高麗縁(こうらいべり)」というもので上質さを表わす。
図1から約50年後に描かれた『慕帰絵詞』から、図2、3の壁に掛けた仏画の前に置いた卓(前机)が床の間の起源である。書院造以前の部屋の様子がおよそ想像できる。卓の上には三具足(香炉、花瓶、燭台)を置いた。やがて図4のように、卓が造り付けの床(押板)になる。もとは仏教に基づく「供花(くげ)」であったものが、図5の桜のように、徐々に宗教的色彩から離れ、装飾的な供花からやがては、鑑賞性をもつ「いけばな」へと急速に変貌していった。こうした供花から座敷飾りの形式が完成するのが室町後期、将軍足利義政を中心とする東山時代だった。
中国との交易と会所という場の文化
村井氏は、15代におよぶ足利将軍家において、北山文化の義満、東山文化の義政の間にあって目立たないが、6代将軍義教の会所文化を過小評価してはならないと指摘している。会所は義教以前に5宇が存在し、自身で3宇を建設し、この8宇をフル活用していた。和歌・連歌・茶の湯などを月次の例会にしている。このような義教時代の文芸・芸能文化を「永享文化」と名付けられている。前期の北山、後期の東山の間にあって、応仁の乱以前の、まさに室町期を代表する「室町文化」と呼んで差し支えないと村井氏は強調している。
いけばなの歴史における室町時代の評価の中で、工藤昌伸は、当時大量に輸入されていた唐物(からもの)の器類(花器)が日本のいけばなの初期の形態に大きな影響を与えたことに注意をすべきだと指摘している(『いけばなの道』)。ここでも義教は重要な役割をしていて、義持以来、一時中断していた日明貿易を復活させ唐物の流通を促進している。
唐物とは、中世から近世にかけて尊ばれた中国(宋、元、明、清)の美術品を指す。平安時代(日宋)、鎌倉(日元)、室町(日明)、江戸(日清)と相手は変わるものの、唐物は珍重された。鎌倉時代、禅宗や喫茶の習慣が日本に広まり、茶道具が唐物の重要な物品となっていく。室町時代には権威化が進む(同朋衆が目利きをした)。応仁の乱後は幕府財政の逼迫し、足利義政は蒐集した唐物(「東山御物」、名物)を放出するといった流れがある。初期の花器にはさまざまな素材と形があったため、それぞれに合わせて花を立てるには高度な技術が必要だったと思われる(大井ミノブ『いけばなの歴史』)
いけばなは室町時代、天皇・朝廷のたて花(僧侶の花)と幕府・将軍の会所という「場」において、その座敷飾りから発展してきた(同朋衆の花)。そこからやがて単独で鑑賞されるようになり、現代、とくに戦後は芸術としての道を進んだわけだが、現代の生活文化のなかの花、あるいは、SNS時代の花という観点からみると、ふたたび「座」としてのコミュニティやその「場」を飾り愉しむ花の重要性が増してきているように思えてくる。言い換えれば、花が置かれる場所、使われ方、そして花器について考えることがますます重要になっているということである。
※参考
○ 『生活からみた いけばなの歴史』 大井ミノブ 主婦の友社 1964
○ 『いけばなの道』 工藤昌伸 主婦の友社 1985
○ 『「花」の成立と展開』 小林善帆 和泉書院 2007
○ 『花と茶の世界: 伝統文化史論』 村井康彦 三一書房 1990
○ 『春日権現記』 鎌倉時代末(1309)第15軸 国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287500
○ 『墓帰絵詞』南北朝時代 国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2610688
○ 『いけばな総合大事典』主婦の友社 1980 から 【供花】の項目(p245,246)
○ 『日本常民生活絵引』新版 渋沢敬三、神奈川大学日本常民文化研究所 編 平凡社 1984
○ 『一本草 花が教える生きる力』 珠寳 徳間書店 2016
○ 松岡正剛 「千夜千冊」 https://1000ya.isis.ne.jp/0520.html